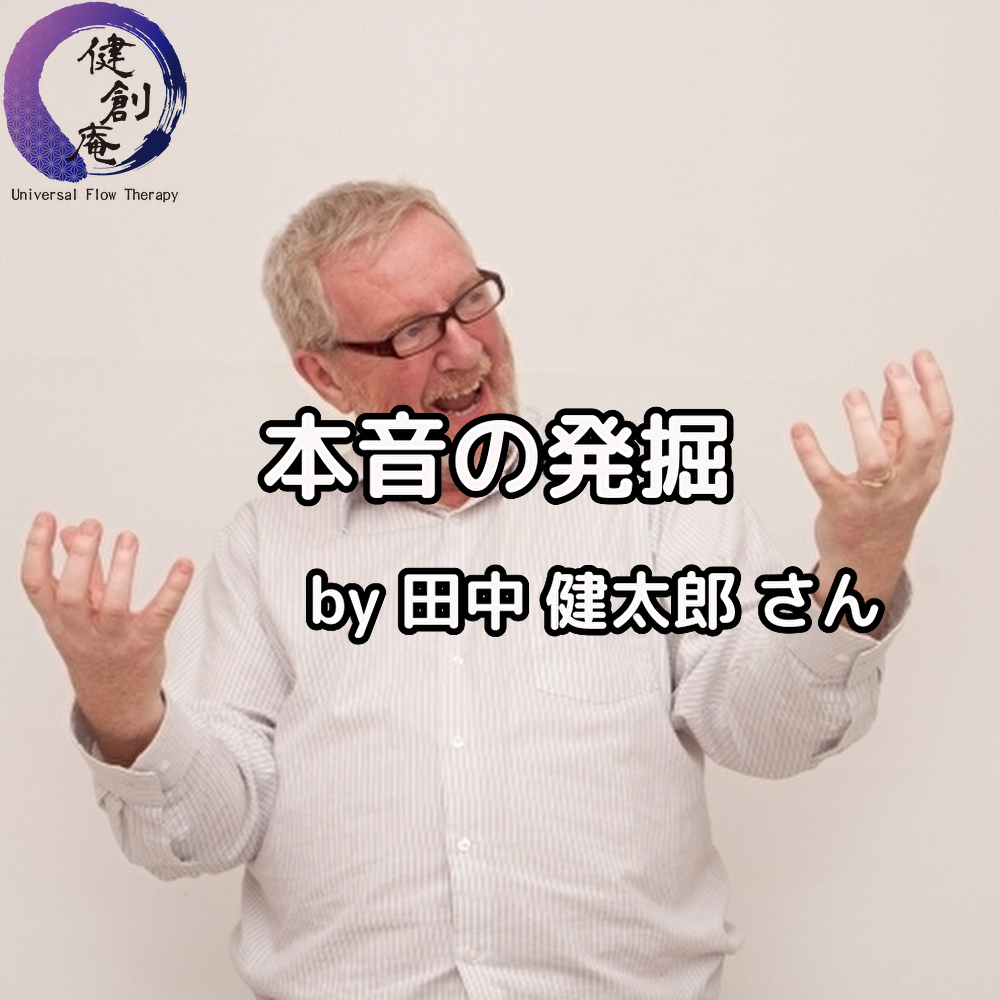家族との対話
オンライン面談から数日後の夕食時。健太郎は家族と食卓を囲んでいた。妻の恵美子、娘の恭子、息子の健太。それぞれの顔を見ながら、先日の「ライフプロファイリング」の話を切り出そうとしていた。
「先日聞いたんだけどな。『ライフプロファイリング』って知ってるか?」
家族は首をかしげる。そのまま続けた。
「ライフプロファイリングは、誕生日や血液型などの情報から個人の特性を分析する手法で、約20年前から研究が進められているらしいよ。占いではなく、データの意味さえ分かれば誰にでも読み解けるんだ。人にはそれぞれ、生まれ持った色や性質があるんだ。例えば、私は『赤海公』なんだって」
恵美子が興味深そうに尋ねた。
「それって、どういう意味なの?」
「赤は情熱、海は包容力、公は社交性を表すらしい。だから、情熱的だけど周りとの調和も大切にする性格なんだとか」
恭子が微笑みながら言った。「お父さんらしいね」
家族の色
私は少し照れながらも、家族一人ひとりの色について話し始めた。
「お母さんは『紫炎空』。紫はアイディア力・炎は情熱・空は自由を表す。だから感性が豊かで、自由な発想を持っているんだ。」
恵美子は驚いた表情を浮かべた。
「そんなふうに言われると、なんだか照れくさいわね。そういえば、昔から新しいアイデアを考えるのが好きだったわ」
「恭子は『緑炎空』。なんと3人とも、色が違うだけで3つのうち2つが同じだって。310億パターンだから同じ箇所があるだけでも稀なのに、やっぱり親子なんだな。
緑は調和。人との調和を大切にしながら、情熱を持って自由に生きるタイプだそうだ。自由に生きたいからこそ、意味づけをして価値を見出したくなるんだろうな」
恭子は笑顔で答えた。
「なんだか、私のことをよく知ってるみたい。だから人との調和を大切にしながらも、情熱を追求してきたのね」
「健太は『黄炎空』。黄色は好奇心。新しいことに興味を持ち、情熱的に取り組む自由人だってさ。健太の場合特に、感情豊かだからよく出てきてるよな」
健太は照れくさそうに頭をかいた。「へぇ、なんか俺らしいかも。新しいことに挑戦するのが好きなのは、そのせいかも」と笑う。
家族の絆と自己理解
・私の「赤海公」の情熱と包容力が、家族の中心としての役割を果たしている。
・恵美子の「紫炎空」の自由な発想が、家族に新しい風を吹き込んでいる。
・恭子の「緑炎空」の調和を重んじる性格が、家族のバランスを保っている。
・健太の「黄炎空」の好奇心旺盛な姿勢が、家族に活気を与えている。
健太郎は家族の色を知ることで、改めて家族の個性や魅力に気づいた。それぞれが持つ色や性質が、家族の絆をより深めていることを感じた。かつ私自身の色を再認識することで、家族との関わり方にも変化が生まれ始めていた。
職人時代に「3軒建ててみれば分かる」と師匠から教わったことを思い出した。私自身、社員たちに言ってきたことだ。経験を通じて自己理解が深まっている。今回も、家族を通じて自分を顧みることができた。「自分を知る」なかなかおもしろい。
「これからは、お互いの色を尊重しながら、もっといい家族になっていこう」の言葉に、家族全員がうなずき、笑顔を交わした。社員のことも把握してみたら、より理解が深まっていい関係が築けそうだ。尊重し合うことで、より深い理解とつながりが生まれてるだろう。
理解するほどに深みが増してくる予感に、期待と不安が入り混じっている。今までにないワクワクした気持ちが芽生えてきた。