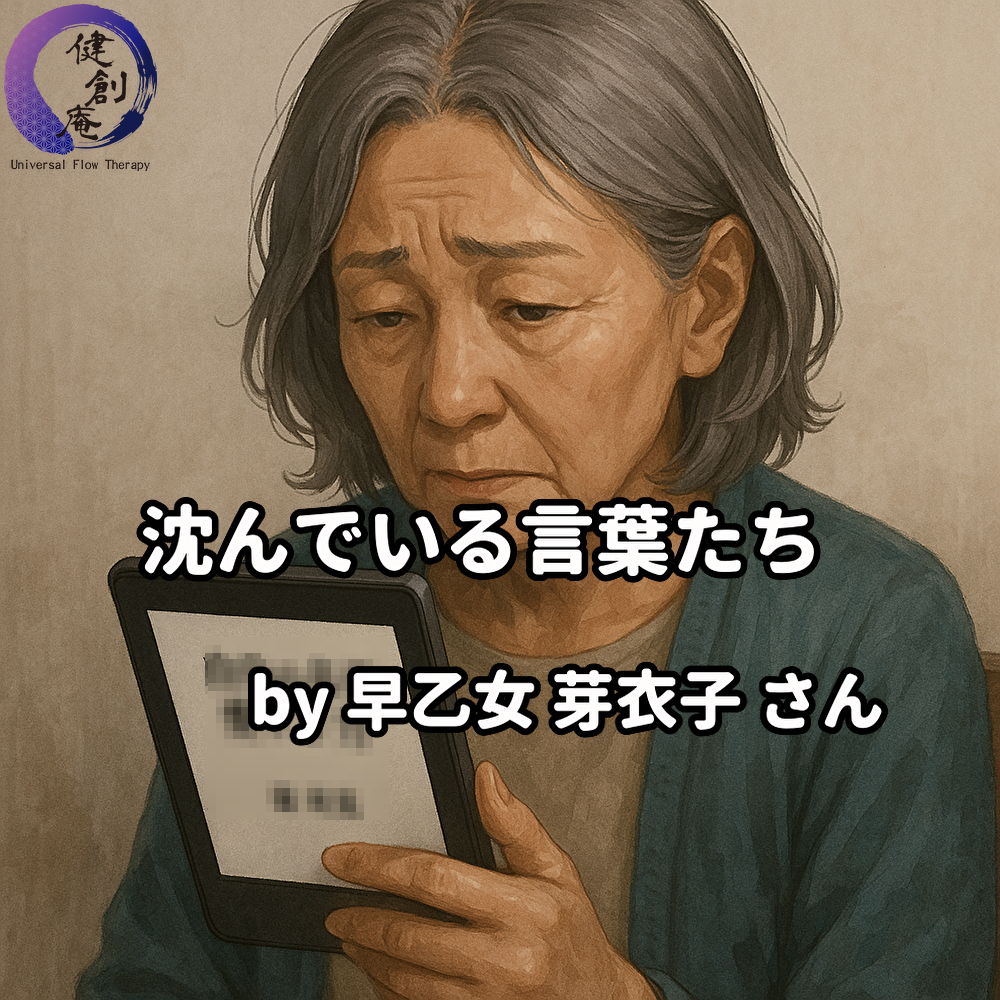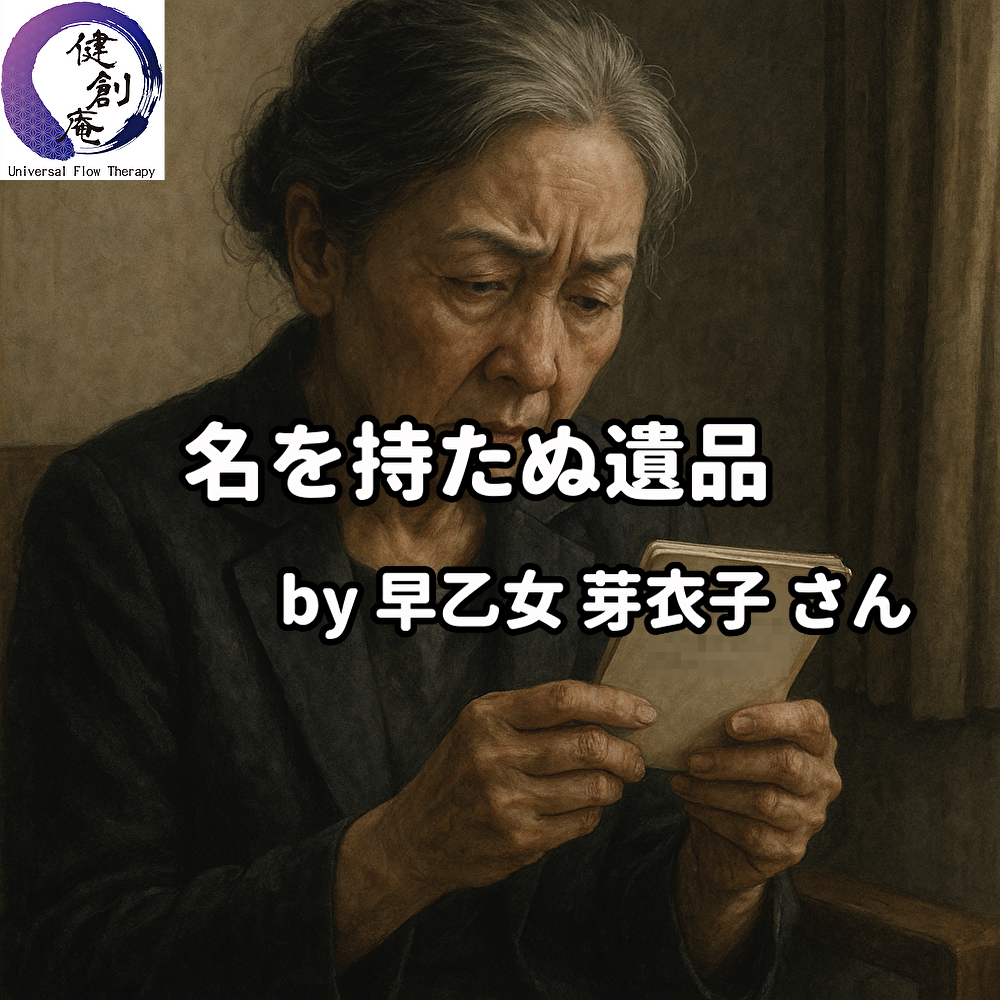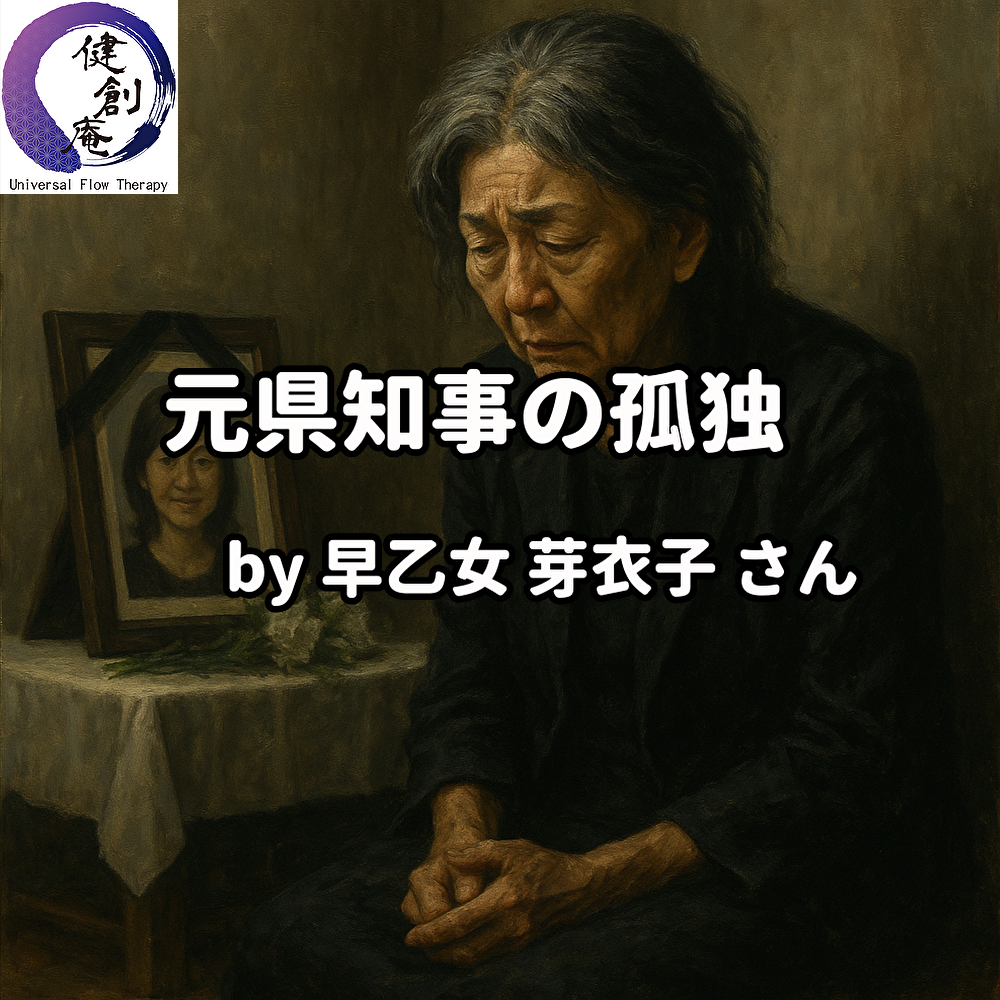問いの解像度
夜、久々にぐっすり眠れた。泣いたあと、心は静かで穏やかだ。感情が嵐のように吹き抜け、今は凪のよう。泣けたことで感情解放できた手応えがある。「健全な精神は、健康な体から」とよく言われるが、まさにそのとおりだと実感している。
朝5時。目が覚めて、しんと静まり返ったベッドの上で、天井を見つめながら考えている。
「私は・・・何を分かっていたのか?」
娘の名前――優花。名づけたのは私だ。でも、その名前に込めた意味を、自分の口からちゃんと語ったことがあっただろうか?誰かに訊かれて、答えたことはあるかもしれない。でも、あの子に向かってまっすぐに「あなたの名前はね」と話した記憶を、どうしても思い出せない。
穏やかな静けさが、なおのこと苦しい。答えがないからではない。問いの解像度が、水アカがついた磨りガラスのまま。意識はハッキリしているのに、「名前ってなに?」という問いの輪郭だけが、いつまでも胸の奥に残り続けている。まるで、娘が今も問いかけてくるように。
本当の言葉
ベランダに出てみた。空気は冷たく、晴れて澄み渡っている。頬を撫でる心地よい風に、ようやく深く呼吸できた気がする。
「私は、あの子に何を伝えたかったのだろう?」
ずっと「正しさ」に縛られて生きてきた。政治の世界で、たった1回の失言で命取りになる場面を何度も見てきた。だからこそ、いつしか言葉を選ぶ癖がつき、感情を飲み込むようになっていたのかもしれない。

あの子は本当の言葉を求めていたのだ。取り繕わない、傷つこうが悩んでいようが、絶対に揺るがない魂からの言葉。分かっていなくても、分かろうとする姿勢。それを、ずっと見せられなかった。
いなくなった今、優花にかけてあげたい言葉を探すも、一向に出てこない。何を言ってもうわべだけの、納得には遠く及ばない気がしてならない。
再出発の教本
Kindle端末は、今もリビングのテーブルに置かれている。『自分の名前を愛する力』あの本は、もはや「読み終えた本」ではなくなっていた。
娘が残した問いを、私が今ようやく引き継いだという証。私にとって『自分の名前を愛する力』は、娘の遺書ではない。再出発の教本なのだ。
泣いたことも、痛んだことも、決して無駄にはしたくない。あの子の問いとともに、もう一度、人生を考え直していく。名前を、そして私自身を。
考えに考えてみて分かったことがある。いくら考えても、現状では優花への言葉を紡ぎ出すことは無理だ。龍先生に助けを求めてみてもいいのではないか?と考え至ってきた。
「龍 庵真 様
はじめまして。
先生の著書を読ませていただき、大変感動しております。
困っていることがあり、相談させていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
早乙女 芽衣子」
メッセンジャーで送ってみた。この送信ボタンを押すのに、勇気を要した。私は今、問いを抱えたまま進もうとしている。あの子の問いに、今度こそ私なりの答えを生きていくために。